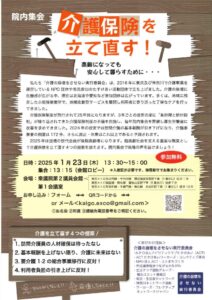3月議会一般質問「包括的な相談支援の構築に向けて 」
生活に困窮している人たちの「セーフティネット」として、生活保護に至る前の相談支援の充実を目的とした「生活困窮者自立支援制度」開始から10年が経ちました。しかし、市民が抱える暮らしの課題は、コロナ禍を経て、より複雑化しています。既存の制度・福祉サービスを活用しつつ、ワンストップで生活全般に渡る、「包括的な支援を提供する仕組みづくり」が求められています。
神奈川県座間市では、制度施行から「断らない相談支援」を理念として掲げ、複雑に絡み合う市民の課題に対して、市役所の機能を活かし、地域との連携、協働の具体的な取り組みがされており、新たな生活困窮者自立支援法の枠組みの中で注目されています。
昨年、座間市の地域福祉課に伺い、包括的支援の取り組みについてお話を伺いました。生活困窮者自立支援制度を開始した当初に、「包括的な支援を提供する仕組みづくり」のために、担当課が全庁をまわり、生活困窮者自立支援制度のことを伝えるとともに、各課における「相談」の課題を集めたとのことでした。
具体的な例では、税の滞納相談に来られた方が、その後自立サポート部署につなげたことで就労することができ、感謝されたということです。そういった職員の成功体験を庁内で共有し、包括的な支援の仕組みづくりとして、相談支援の庁内連携のツールである「つなぐシート」をつくり、全職員が研修を受け、市民の困りごとへの「気づき」を養成しています。
府中市では、地域包括支援センターや、地域福祉コーディネーターによる相談支援が行われ、府中市役所に「福祉総合相談窓口」が設置されています。2025年度の予算案で市は、「子どもや、障害者、高齢者、生活困窮者など、属性を超えた相談対応や支援にあたり、包括的に提供できる体制の構築をするための重層的支援体制整備事業に着手する」とのことでしたが、今後の包括的な相談支援の充実を求めて一般質問しました。
市は、組織を再編して、福祉や生活の困りごとをワンストップで対応する相談窓口として、福祉総合相談窓口を置いたということでしたが、窓口が実質対応した相談件数は、2023年度で36件、2024年度12月まで17件です。ワンストップの相談窓口としての役割を果たしているのか、包括的な相談支援の構築が進んでいるのか、福祉に関する統括のセクションになっているのかをさらに質問したところ、「福祉総合相談業務におきましては、現在、つなぎ先の相談支援機関と情報共有に使用する共通のマニュアルやツールについて、持ち合わせていない」との答弁でした。具体的なしくみづくりを進めていかない限りは、包括的な相談支援の実現は困難です。
重層的支援体制整備事業においては、さまざまな実施主体による包括的なネットワークによる「チーム支援」で福祉総合相談を担っていくということ、職員配置の拡充と、外部から専門職員を配置するということですが、包括的な相談支援に向けては、相談機能がある部署だけではなく、全庁参画での協議体の構築、断らない相談のための具体的な情報共有ツールの開発、職員一人ひとりが困りごとを「気づく」ための研修体系つくりが必要です。
全庁参画で、地域の民間支援団体との連携も進め、どんな困りごとでも受け止められる体制づくりを、市が主体となり進めていくべきと訴えました。